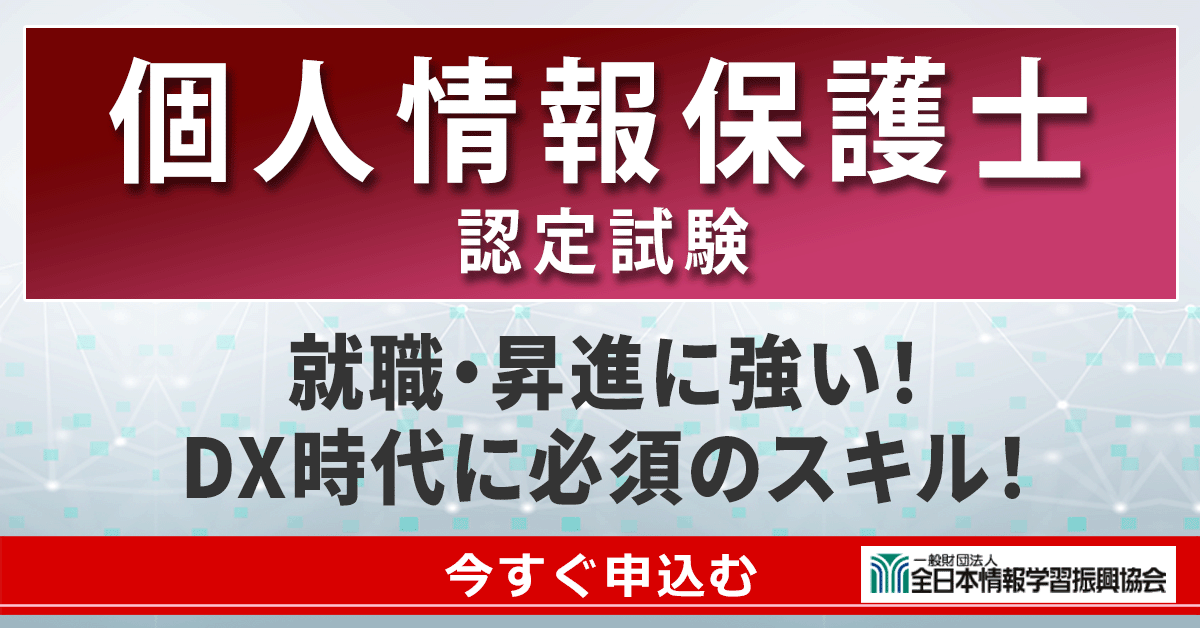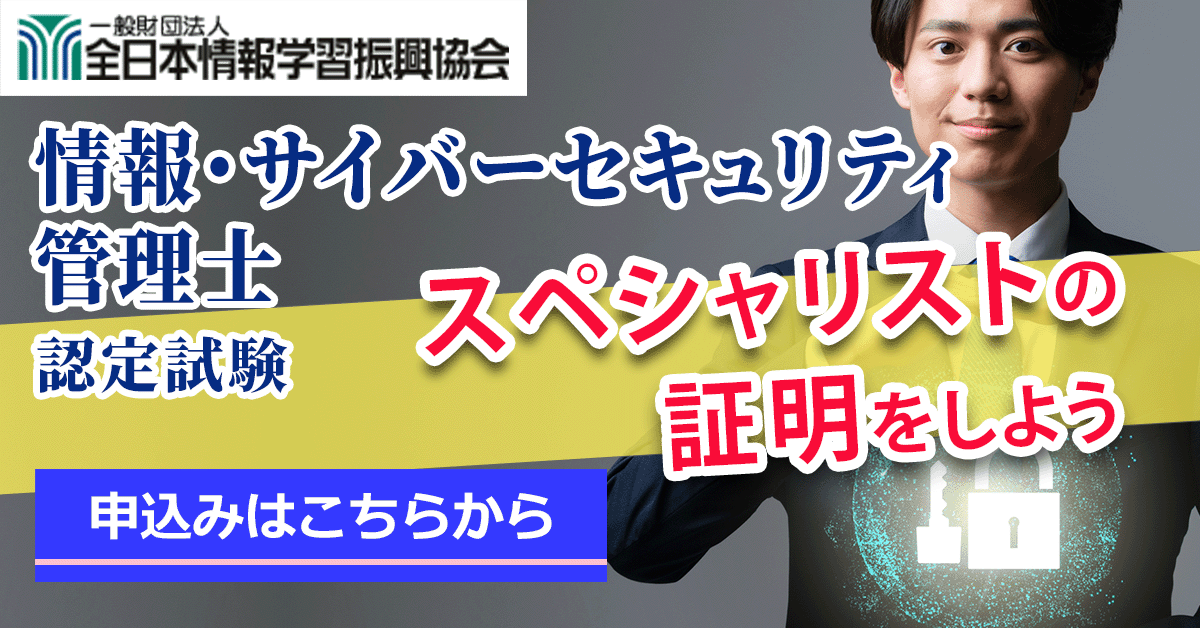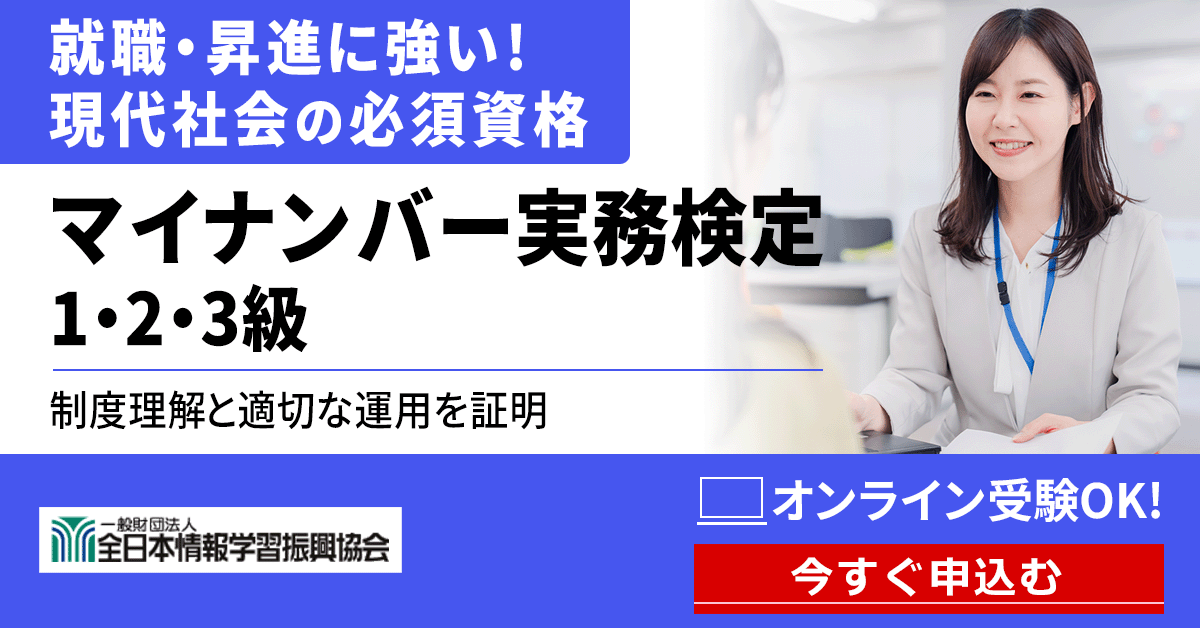民間資格
事務・ビジネス・経営
個人情報保護士認定試験

個人情報保護の専門家としての道を開く資格
個人情報保護士認定試験は、個人情報の適切な管理と運用を行う専門家を認定する民間資格です。高度情報化社会において、個人情報の保護はますます重要視されており、この資格を取得することで、個人情報漏洩のリスクを軽減し、企業や組織の信頼性を高めることができます。試験は筆記試験で、個人情報保護法やマイナンバー法に関する知識が問われます。法律系の資格は難解なイメージがありますが、出題範囲が明確であるため、計画的に学習を進めやすいのが特徴です。合格率は約37.7%で、しっかりとした準備をすれば合格が狙えます。個人情報保護士の資格は、民間企業や地方自治体など、幅広い分野で活用され、特に法務や人事、総務などの職種での需要が高まっています。今後、個人情報保護に対する意識が高まる中で、この資格の重要性はさらに増すでしょう。
詳細情報
受験の条件 | この試験には、年齢、学歴、職歴などの制限は一切ありません。誰でも申し込み・受験が可能であり、学生から社会人まで幅広い層の受験者に対応しています。 特に、以下のような方に適した資格といえるでしょう。 ・情報システム部門、総務・法務部門で個人情報を扱う業務に従事している方 ・コンプライアンス担当、リスクマネジメント担当として組織のガバナンスに関わる方 ・個人情報やマイナンバーを取り扱う業務委託先事業者 ・教育機関・医療機関・自治体などで個人情報の適切な管理を求められる方 ・就職・転職活動に向けて客観的なスキル証明を得たい方 また、団体受験制度もあるため、組織的な研修に導入されるケースも多く見られます。 |
|---|---|
試験方法 | 筆記試験を通じて個人情報保護に関する知識を評価。 |
試験日程 | 個人情報保護士認定試験は、年間を通じて複数回実施されています。公式に定められた統一試験(公開会場受験)は、春・夏・秋・冬の年4回程度で、通常は以下のようなスケジュールが採用されています。 春季(3月~4月頃) 夏季(6月~7月頃) 秋季(9月~10月頃) 冬季(12月~1月頃) また、試験の実施形態によって日程は異なり、次の3つの方式が選べます。 公開会場受験(紙の試験用紙による筆記) CBT受験:全国170か所以上のテストセンターでPCを使用 IBT受験:自宅などからインターネット経由で受験 |
試験開催地 | 公開会場受験は、以下の都市を中心に実施されます。 北海道(札幌) 東北(仙台) 関東(東京、横浜) 中部(名古屋) 近畿(大阪、京都、神戸) 中国(岡山) 九州(福岡) CBT受験は全国のテストセンターにて実施され、地域による受験機会の偏りが少ないことが特徴です。IBT形式では自宅からの受験が可能であり、時間的・地理的制約の少ない受験が実現されています。 |
受験料 | 一般:11,000円(税込) 学割:8,800円(税込) その他各種割引ありがあります。 |
免除科目 | |
登録・更新 | ホームページを確認ください。 |
主催団体 |
一般財団法人全日本情報学習振興協会 試験の詳細/お申込みはこちら |
試験内容
試験は、以下の2つの課題に分かれており、各課題50問、合計100問のマークシート式です。試験時間は150分です。
課題Ⅰ:個人情報保護法とマイナンバー法の理解
こちらは法律の理解が中心となります。以下のような内容が出題されます。
・個人情報保護法の目的・理念
・定義(個人情報、個人データ、保有個人データ 等)
・取扱事業者の義務(取得・利用・第三者提供・開示請求)
・番号法(マイナンバー制度)とその利用範囲
・行政機関、公的機関における取扱い
・近年の判例や個人情報漏洩事件、ガイドラインとの関係
特に、2022年施行の改正法以降、個人関連情報や仮名加工情報などの新しい定義の理解も求められています。
課題Ⅱ:個人情報保護の対策と情報セキュリティ
こちらは、現場での情報セキュリティ対応に関する実践力が問われます。
・組織的・人的・物理的・技術的安全管理措置の基礎と応用
・情報漏洩リスクとリスクアセスメント
・セキュリティポリシーと教育訓練の設計
・システム管理、アクセス制御、通信の暗号化
・通報制度、インシデント対応と再発防止策
企業のコンプライアンスや監査の場面で求められる対応方法を、実際のケーススタディ形式で問う設問も多く、机上の知識だけでなく現場を想定した理解が必要です。
課題Ⅰ:個人情報保護法とマイナンバー法の理解
こちらは法律の理解が中心となります。以下のような内容が出題されます。
・個人情報保護法の目的・理念
・定義(個人情報、個人データ、保有個人データ 等)
・取扱事業者の義務(取得・利用・第三者提供・開示請求)
・番号法(マイナンバー制度)とその利用範囲
・行政機関、公的機関における取扱い
・近年の判例や個人情報漏洩事件、ガイドラインとの関係
特に、2022年施行の改正法以降、個人関連情報や仮名加工情報などの新しい定義の理解も求められています。
課題Ⅱ:個人情報保護の対策と情報セキュリティ
こちらは、現場での情報セキュリティ対応に関する実践力が問われます。
・組織的・人的・物理的・技術的安全管理措置の基礎と応用
・情報漏洩リスクとリスクアセスメント
・セキュリティポリシーと教育訓練の設計
・システム管理、アクセス制御、通信の暗号化
・通報制度、インシデント対応と再発防止策
企業のコンプライアンスや監査の場面で求められる対応方法を、実際のケーススタディ形式で問う設問も多く、机上の知識だけでなく現場を想定した理解が必要です。
参考教材のご紹介